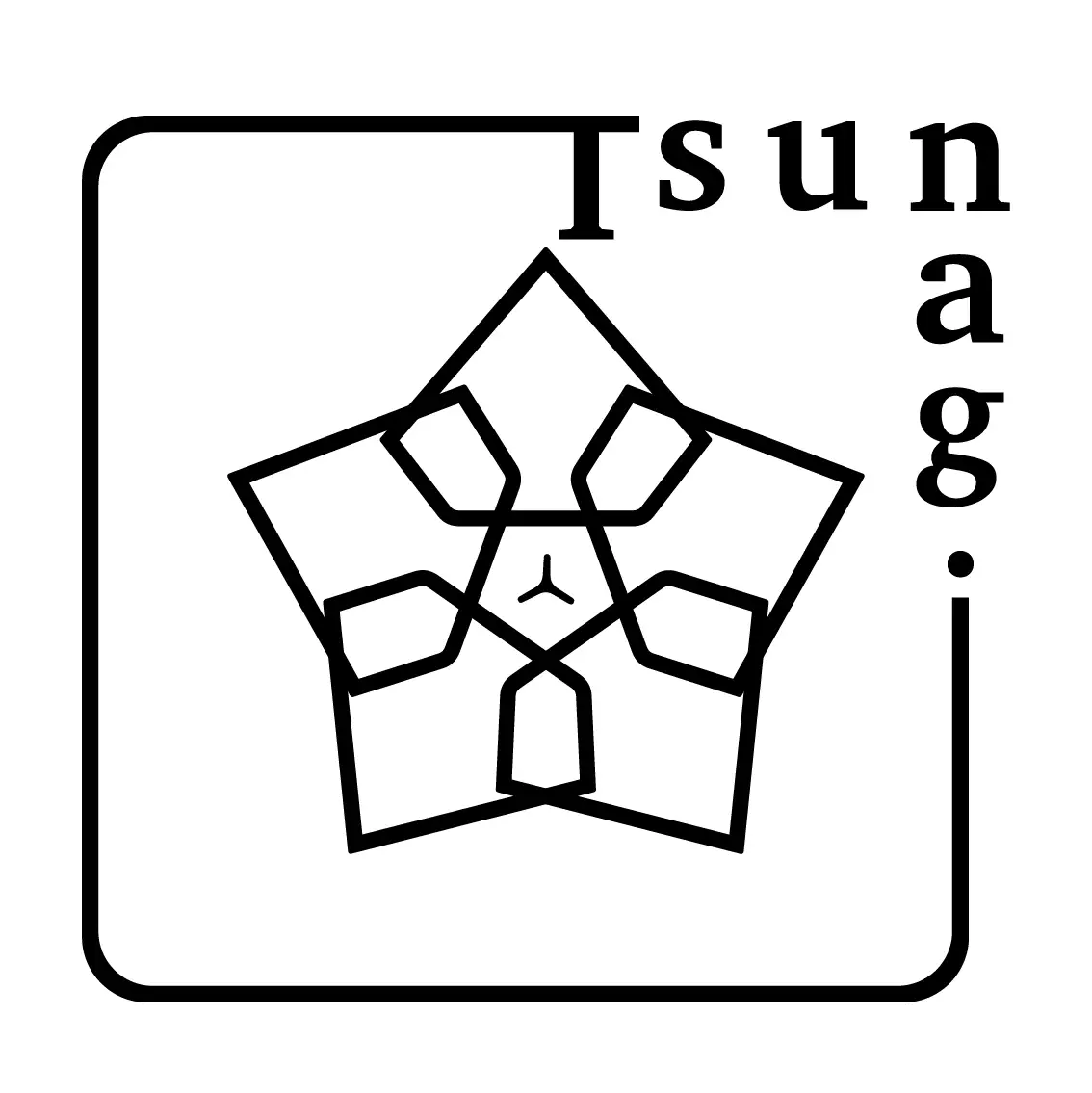味わい、そして満ちて生きる
文化を次世代へつなぐ
Tsunagiは、蕎麦を起点に人と地域、都市と一次産業をつなぎ、効率中心の社会の中で見失われがちな“人間らしい豊かさ”を取り戻すことを目指しています。
「好き」という感情を原動力に、自然や文化との関わりを深めることで、一人ひとりが人生を味わいながら生きられる、そんな未来を私たちは文化として育てていきます。
私たちが目指すのは、単なる経済的な豊かさではなく、人が心から「生きていて良かった」と感じられるような文化的な豊かさです。蕎麦は日本人の暮らしに寄り添い、食を超えて季節や風景、地域の記憶とともに受け継がれてきた文化です。
その蕎麦を軸に、人と人、人と自然、人と地域が出会い交わることで、誰もが「味わい深く」生きられる社会」をつくることができると信じています。
効率や便利さの影で失われた”人間らしさ”を取り戻し、人生の実感を共有し合う。
これがTsunagiの理念であり、すべての活動の根底にある想いです。
「蕎麦が好き」
シンプルな想いがすべての源泉
Tsunagiの始まりは、ただ純粋に「蕎麦が好き」という偏愛から生まれました。
しかしその想いは、人と地域、都市と一次産業をつなぐ大きな可能性を秘めていました。
私たちは、消費者として関わるだけでなく“仲間として共に楽しみ、支え合う関係性”をデザインしています。
一次産業の現場では担い手不足や高齢化が進み、地域社会の持続可能性が揺らいでいます。一方で都市の暮らしは便利さと引き換えに、自然や文化との距離が広がっています。
Tsunagiはこの二つの断絶を「楽しいからやってみたい」というシンプルな動機で橋渡しをしています。
ふとした好奇心から参加した人が、気づけば仲間となり、地域や農業を応援する存在になっていく。
そんな “共感の循環”を蕎麦から育てることが、私たちの目指す姿です。
設立の経緯
Tsunagiは、“蕎麦をもっと身近にもっと楽しく広めたい”という想い始め、農家さんや地域との出会いを通じて大きく広がっていきました。
製粉の過程で大量に破棄されていた副産物「ふすま粉」をクラフトビールにアップサイクルしたプロジェクト等で、持続可能性と社会課題解決を両立しました。
また、蕎麦畑を自分の畑として体験できる「蕎麦畑オーナーシップ」プロジェクトは都市生活者と農業をつなぎ、農家支援や関係人口拡大につながりました。
蕎麦打ちと音楽カルチャーを組み合せたプロモーションや、子ども向けの食育ワークショップなども生まれ、蕎麦は“食材”から「文化と未来をつなぐプラットフォーム」へと進化しました。
偏愛が社会課題と結びつき、課題解決が新しい楽しさを呼び込む。この循環こそがTsunagiの歩みそのものです。

活動内容
蕎麦畑オーナーシップ
畑を自分のものとして育て、収穫し、味わい、
そして農家とつながる体験プログラム
都市に暮らす人が、農業と出会い、自分ごと化できる仕組みとして生まれました。参加者は、自分の畑を持つような感覚で、蕎麦を育て、収穫し、味わうことで、農業が「遠いもの」から「自分ごと」へと変わります。参加者が “応援者”へと変わるきっかけを創っています。

メディア発信
物語を届け、仲間を増やし、共創の輪を広げる
「そば色ノ日々」(ブログ)や「ズズズッRadio」では、蕎麦にかかわる人々の多い、地域文化の魅力、背景にあるストーリーを丁寧に伝え、人と地域の物語を広く届けています。
ストーリーが共感を生み、共感が参加を生み、参加が、また地域と文化を支える力になる。
メディア発信は、仲間を増やし、共創の輪を拡大するTsunagiの活動を支える大切な手段であり、Tsunagiの活動全体を支える大切な基盤です。